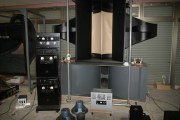2010.03.24 水曜日 22:04
読書週間
一日に何度か、猛烈なドライブのかかった母親の物忘れに驚かされることを除けば、会津の早春は穏やか。母の車のタイヤも履き替えてしまったし、あまりの切れ味の悪さにこちらの血管が切れそうになるハサミと包丁数本を研ぎ上げたことの他には、大したこともせずにゆったりと過ごした。
今回の帰省では、研究室で日々増殖し続ける蔵書の中から以下の三冊を持ってきた。先ほど、親鸞の下巻を読了し、質・量ともに大いに満足できる読書週間を終えた。
「親鸞」は五木寛之が地方紙に連載した小説。昨年、初めて新聞小説(宮部みゆきの時代物)というものをまじめに読んだ。それまでは単行本になるのを待って一気に読むことを是としていたからだが、今回の「親鸞」は、やはり単行本で読むのがよいと思う。自分の都合で途中で止めるのは仕方がないが、「明日の朝刊まで読めない」などという状態は辛すぎる。
物語は、親鸞の幼少期から越後配流までの正に半生を描くもので、史的な事象の描写、表現にはいささか気になることもあるが、専修念仏という思想が確立していく過程を、まざまざと見る思いだった。神や仏のいない現代における発心とか結縁とかは、こういうことかもしれないと思う。
二・二六事件で青年将校たちに強い影響を与えた予備役少将齋藤瀏。彼と娘の史の言葉と短歌を通じて見る「二・二六」とその後には、これまでの研究史で必ずしも明らかにされてこなかった、思想以前の心情が陰影も鮮やかに浮かび上がる。
明日は移動日。早くも新年度の足音が…。
今回の帰省では、研究室で日々増殖し続ける蔵書の中から以下の三冊を持ってきた。先ほど、親鸞の下巻を読了し、質・量ともに大いに満足できる読書週間を終えた。
「親鸞」は五木寛之が地方紙に連載した小説。昨年、初めて新聞小説(宮部みゆきの時代物)というものをまじめに読んだ。それまでは単行本になるのを待って一気に読むことを是としていたからだが、今回の「親鸞」は、やはり単行本で読むのがよいと思う。自分の都合で途中で止めるのは仕方がないが、「明日の朝刊まで読めない」などという状態は辛すぎる。
物語は、親鸞の幼少期から越後配流までの正に半生を描くもので、史的な事象の描写、表現にはいささか気になることもあるが、専修念仏という思想が確立していく過程を、まざまざと見る思いだった。神や仏のいない現代における発心とか結縁とかは、こういうことかもしれないと思う。
二・二六事件で青年将校たちに強い影響を与えた予備役少将齋藤瀏。彼と娘の史の言葉と短歌を通じて見る「二・二六」とその後には、これまでの研究史で必ずしも明らかにされてこなかった、思想以前の心情が陰影も鮮やかに浮かび上がる。
明日は移動日。早くも新年度の足音が…。