2010.03.20 土曜日 23:38
どっこいオーディオ機器を作る
冬と春が覇権を競っているような天気のせいか、三女が喉を腫らしてしまった。ひどく咳き込むのを心配した母が動物病院に連れて行き、例によって親切丁寧な治療の効果はてきめんで、苦しそうに咳き込むこともなくなった。冷酷無比な請求書は目をつぶって丸呑みするしかない。
番外編 「エイフル」に行ってきた
彼岸の親戚廻りは早々と終えたので、昨夏から行きたいと思いつつ果たせなかったヴィンテージオーディオショップ「エイフル」を訪ねてみた。昨年、埼玉から会津、裏磐梯に移ってきたのだが、夏、秋は自由な時間がとれず、冬は豪雪地帯を走破する元気がなく、折から南風が流れ込んで20℃近くまで気温が上がった今日、エイヤっと出かけてみた。お目当ては、元日本オーディオ協会会長浅野勇氏設計のアンプ。
真空管は、発明からわずかに100年で消えてしまった「技術」だが、その100年の間には関連技術の大きな進歩があった。浅野氏が活躍された頃と現在とでもっとも違うところは、ダイオードとコンデンサではないかと思う。整流と平滑に使うこれら部品が大きく進歩するのは、浅野氏の時代の少し後。後の時代の優れた部品を使えば、必ずより良い音が出るのか、前時代の回路構成は後のものに劣るのかという厄介な問について、浅野アンプの音を聴くことで何かヒントを得られるかもしれない。
エイフルの場所は、地図で見る限り私の「遊び場」の中だから、実家から30分ほどで到着。あらかじめ電話で希望を伝えておいたので、着くとすぐに、浅野アンプ の音を聴かせてもらえることになった。このアンプ、最近売られている完成品、キットいずれにもほとんど採用されない「当時」の技術、技法で構成されており、無音時にはハムノイズが聞こえる。もっとも、つながっているスピーカーも時代物
の音を聴かせてもらえることになった。このアンプ、最近売られている完成品、キットいずれにもほとんど採用されない「当時」の技術、技法で構成されており、無音時にはハムノイズが聞こえる。もっとも、つながっているスピーカーも時代物 で大変に効率がよい(100dbを越えているはず)ものだから、私が持っているどのアンプ(除くトランジスタ)でも必ずハムが聞こえるだろう。で、音が鳴り始めたら、ハムは全く気にならなくなり、すぐに楽音に集中してしまう、というか、引き込まれてしまう。ものすごい迫力と音の艶に圧倒されること頻り。
で大変に効率がよい(100dbを越えているはず)ものだから、私が持っているどのアンプ(除くトランジスタ)でも必ずハムが聞こえるだろう。で、音が鳴り始めたら、ハムは全く気にならなくなり、すぐに楽音に集中してしまう、というか、引き込まれてしまう。ものすごい迫力と音の艶に圧倒されること頻り。
ところが浅野アンプの後に出てきたWestern Electric 59B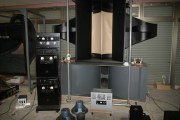 を聴いて、はたと困った。浅野アンプのパーツ一式を購入しようかと思って行ったのだが、59Bの音は(もちろん値段も)比較にならないほどすばらしいのだ。深みというか気品というか、戦前のアメリカの工業技術がこれほど凄まじいとは、正直、肌に粟の立つ思いだった。
を聴いて、はたと困った。浅野アンプのパーツ一式を購入しようかと思って行ったのだが、59Bの音は(もちろん値段も)比較にならないほどすばらしいのだ。深みというか気品というか、戦前のアメリカの工業技術がこれほど凄まじいとは、正直、肌に粟の立つ思いだった。
ショップ兼展示室の内部はまだ整理が終わっていないようで、機器類やユニットが所狭しと置かれているが、ひとつ上のフロアに上がると、「ヴィンテージオーディオ博物館」の雰囲気。いきなりVictrola の美音を聴かせてもらった。この奥には、ものの本やネットでしか見たことのなかった「骨董」がずらりと並び、階下での困惑などとりあえずどこかに置いて、次々と動作する名機に見とれ、聴き惚れる。例えばWestern の7A
の美音を聴かせてもらった。この奥には、ものの本やネットでしか見たことのなかった「骨董」がずらりと並び、階下での困惑などとりあえずどこかに置いて、次々と動作する名機に見とれ、聴き惚れる。例えばWestern の7A というアンプ。聞くところに寄ると1922年製造で、チラッと写っている10Dというスピーカーをつなぐ。出てくるのは、惚れ惚れするような典雅な音。ちなみに製造当時の電源は「電池」。ちなみにこの7Aは、希望すれば買えるらしい。貯金しようかな…。
というアンプ。聞くところに寄ると1922年製造で、チラッと写っている10Dというスピーカーをつなぐ。出てくるのは、惚れ惚れするような典雅な音。ちなみに製造当時の電源は「電池」。ちなみにこの7Aは、希望すれば買えるらしい。貯金しようかな…。
建物の3階に案内してもらい、かつての「遊び場」 の風景を眺める。檜原湖は、一日くらい暖かくなっても冬のままだ。
の風景を眺める。檜原湖は、一日くらい暖かくなっても冬のままだ。
今日の試聴はここまで。浅野アンプの件はペンディングということで日を改めて訪問し、再度、いろいろと聴かせてもらうことにした。そのときには秘蔵のSP盤を持ち込もう。
技術の進歩と音質の関係について、今の時点で言えること。
確かに最新技術で作られた工業製品は優れているが、往事の技術で作られた製品でも、時々の最高の知識を集めたものはやはりすばらしい。そして往事のアンプと往事のスピーカーのように、技術者の想定した組み合わせを再現すると、時代を超えたカップリングより好ましい結果が出ることも珍しくない。
文字にすると当たり前だが、今日、エイフルでこのことを実感した。これからの機器設計に役立つ経験だった。
番外編 「エイフル」に行ってきた
彼岸の親戚廻りは早々と終えたので、昨夏から行きたいと思いつつ果たせなかったヴィンテージオーディオショップ「エイフル」を訪ねてみた。昨年、埼玉から会津、裏磐梯に移ってきたのだが、夏、秋は自由な時間がとれず、冬は豪雪地帯を走破する元気がなく、折から南風が流れ込んで20℃近くまで気温が上がった今日、エイヤっと出かけてみた。お目当ては、元日本オーディオ協会会長浅野勇氏設計のアンプ。
真空管は、発明からわずかに100年で消えてしまった「技術」だが、その100年の間には関連技術の大きな進歩があった。浅野氏が活躍された頃と現在とでもっとも違うところは、ダイオードとコンデンサではないかと思う。整流と平滑に使うこれら部品が大きく進歩するのは、浅野氏の時代の少し後。後の時代の優れた部品を使えば、必ずより良い音が出るのか、前時代の回路構成は後のものに劣るのかという厄介な問について、浅野アンプの音を聴くことで何かヒントを得られるかもしれない。
エイフルの場所は、地図で見る限り私の「遊び場」の中だから、実家から30分ほどで到着。あらかじめ電話で希望を伝えておいたので、着くとすぐに、浅野アンプ
 の音を聴かせてもらえることになった。このアンプ、最近売られている完成品、キットいずれにもほとんど採用されない「当時」の技術、技法で構成されており、無音時にはハムノイズが聞こえる。もっとも、つながっているスピーカーも時代物
の音を聴かせてもらえることになった。このアンプ、最近売られている完成品、キットいずれにもほとんど採用されない「当時」の技術、技法で構成されており、無音時にはハムノイズが聞こえる。もっとも、つながっているスピーカーも時代物 で大変に効率がよい(100dbを越えているはず)ものだから、私が持っているどのアンプ(除くトランジスタ)でも必ずハムが聞こえるだろう。で、音が鳴り始めたら、ハムは全く気にならなくなり、すぐに楽音に集中してしまう、というか、引き込まれてしまう。ものすごい迫力と音の艶に圧倒されること頻り。
で大変に効率がよい(100dbを越えているはず)ものだから、私が持っているどのアンプ(除くトランジスタ)でも必ずハムが聞こえるだろう。で、音が鳴り始めたら、ハムは全く気にならなくなり、すぐに楽音に集中してしまう、というか、引き込まれてしまう。ものすごい迫力と音の艶に圧倒されること頻り。ところが浅野アンプの後に出てきたWestern Electric 59B
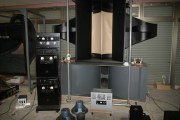 を聴いて、はたと困った。浅野アンプのパーツ一式を購入しようかと思って行ったのだが、59Bの音は(もちろん値段も)比較にならないほどすばらしいのだ。深みというか気品というか、戦前のアメリカの工業技術がこれほど凄まじいとは、正直、肌に粟の立つ思いだった。
を聴いて、はたと困った。浅野アンプのパーツ一式を購入しようかと思って行ったのだが、59Bの音は(もちろん値段も)比較にならないほどすばらしいのだ。深みというか気品というか、戦前のアメリカの工業技術がこれほど凄まじいとは、正直、肌に粟の立つ思いだった。ショップ兼展示室の内部はまだ整理が終わっていないようで、機器類やユニットが所狭しと置かれているが、ひとつ上のフロアに上がると、「ヴィンテージオーディオ博物館」の雰囲気。いきなりVictrola
 の美音を聴かせてもらった。この奥には、ものの本やネットでしか見たことのなかった「骨董」がずらりと並び、階下での困惑などとりあえずどこかに置いて、次々と動作する名機に見とれ、聴き惚れる。例えばWestern の7A
の美音を聴かせてもらった。この奥には、ものの本やネットでしか見たことのなかった「骨董」がずらりと並び、階下での困惑などとりあえずどこかに置いて、次々と動作する名機に見とれ、聴き惚れる。例えばWestern の7A というアンプ。聞くところに寄ると1922年製造で、チラッと写っている10Dというスピーカーをつなぐ。出てくるのは、惚れ惚れするような典雅な音。ちなみに製造当時の電源は「電池」。ちなみにこの7Aは、希望すれば買えるらしい。貯金しようかな…。
というアンプ。聞くところに寄ると1922年製造で、チラッと写っている10Dというスピーカーをつなぐ。出てくるのは、惚れ惚れするような典雅な音。ちなみに製造当時の電源は「電池」。ちなみにこの7Aは、希望すれば買えるらしい。貯金しようかな…。建物の3階に案内してもらい、かつての「遊び場」
 の風景を眺める。檜原湖は、一日くらい暖かくなっても冬のままだ。
の風景を眺める。檜原湖は、一日くらい暖かくなっても冬のままだ。今日の試聴はここまで。浅野アンプの件はペンディングということで日を改めて訪問し、再度、いろいろと聴かせてもらうことにした。そのときには秘蔵のSP盤を持ち込もう。
技術の進歩と音質の関係について、今の時点で言えること。
確かに最新技術で作られた工業製品は優れているが、往事の技術で作られた製品でも、時々の最高の知識を集めたものはやはりすばらしい。そして往事のアンプと往事のスピーカーのように、技術者の想定した組み合わせを再現すると、時代を超えたカップリングより好ましい結果が出ることも珍しくない。
文字にすると当たり前だが、今日、エイフルでこのことを実感した。これからの機器設計に役立つ経験だった。