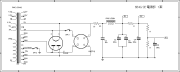2009.03.16 月曜日 23:02
早春の金沢にて
詩的なタイトルだな〜。
加賀百万石の城下町金沢。維新までは、江戸、大坂に次ぐ日本三位の人口を擁し、工芸分野をはじめ、優れた文化を育んだ。今日、「小京都」という表現も見かけるが、小振りの京都などではない。他のどことも違う「金沢」という街なのだ。
今でも金沢は、京、大坂、江戸、そして廻船の寄港する港町の風情を湛える。しかし、どこにも似ていない。どこからも距離的に遠いのだ。今日、金沢には、都会に迫る勢いで人や物が集まる。「最新」「最先端」を求めなければ、とりあえず金沢でなんでも揃う。どこからも遠いから、気安く出かけていけないから、集めてくる意味がある。しかも藩政期以来の伝統で文化に対する受容性が高いから、雑多な物が蝟集しても俗化しきることがない。
要するに、新しい物も大概あって不便を感じることは決してないが、古い物、伝統ある物、文化的な物は、外来の新しい物と対立せず、そのままそこにあり続ける、そういう街なのだ。悲恋の発端や、愛憎の果てにある殺人の舞台に選びたくなる、詩情をかきたててくれる街なのだ。
金沢で、前任大学の卒業式に行った。二年前、オーケストラピットで私の指揮を食い入るように見つめた部員たちが卒業する。彼ら、彼女らの演奏を、初めて客席から聴いた。一つの曲に賭ける熱誠のようなものは、おそらく二年前の方があっただろう。だが技術面では長足の進歩が見られた。遙々出向いた甲斐があった。彼ら彼女らの前途洋々たらんことを。
丸二日半、金沢に滞在し、二度の夕食はゼミのOBOG諸君と再会して、楽しい時間となった。奥の束ねT嬢の功績は相変わらず大きい。食べ物が美味いのはうれしいが、集まってくれる面々と、約一年ぶりという時間を感じさせない和やかな会話が、またうれしい。二日目には、M(夫人)が、昨年生まれた長男を連れてきた。何人目かの「内孫」(「ゼミ生の子供」の意)だ。お約束で抱いてみるが、猫と違ってどう抱いて良いやらわからず、すぐに母親に戻す。ゆっくりと進む会食の間、一度も泣くこともなく(外面が良い)、でもちょっと油断するとテーブルに手をかけ、器をひっくり返して母親をパニックに陥れる(実は意地悪)など、母親であるMに似ているらしい(笑)。
二度の昼食は、「うどんこ」で存分に楽しんだ。温冷それぞれのうどんの風味と、絶妙な出汁は、他の追随を許さぬ絶品といえる。今春、ご主人と女将さんの長女が国立大に合格するという慶事も重なり、会話もまた弾む。姉さん(女将さんのこと)は直前に電話で私の予定を確認し、私の好物だったゴボウの天ぷらを作って待っていてくれた。
笹掻きゴボウのかき揚げ。かけうどんの出汁を吸うと得も言われぬ美味さで、私が金沢に住んでいた頃は、冬期間限定ではあるが通常メニューだった。だがこの天ぷらは、下ごしらえに手間がかかりすぎる。限られた人手では対応しきれなかったのか、この冬、ゴボウのかき揚げは店頭に並ばなかった。私と同様にこの天ぷらが好きな吹奏楽部員が頼み込んでも、駄目だったという。ところが二日間だけ、この天ぷらが店に並んだ。事情を知るバイト学生は「奇跡の二日間」と呼んだ。
二年の歳月で、街はずいぶん、その姿を変えた。だが、大好きな人々の温かさと、暮らしにくくて仕方ないメチャクチャな天気は、少しも変わらず、手厚く、手荒く歓迎してくれた。次はいつ、遊びに行こうか。
加賀百万石の城下町金沢。維新までは、江戸、大坂に次ぐ日本三位の人口を擁し、工芸分野をはじめ、優れた文化を育んだ。今日、「小京都」という表現も見かけるが、小振りの京都などではない。他のどことも違う「金沢」という街なのだ。
今でも金沢は、京、大坂、江戸、そして廻船の寄港する港町の風情を湛える。しかし、どこにも似ていない。どこからも距離的に遠いのだ。今日、金沢には、都会に迫る勢いで人や物が集まる。「最新」「最先端」を求めなければ、とりあえず金沢でなんでも揃う。どこからも遠いから、気安く出かけていけないから、集めてくる意味がある。しかも藩政期以来の伝統で文化に対する受容性が高いから、雑多な物が蝟集しても俗化しきることがない。
要するに、新しい物も大概あって不便を感じることは決してないが、古い物、伝統ある物、文化的な物は、外来の新しい物と対立せず、そのままそこにあり続ける、そういう街なのだ。悲恋の発端や、愛憎の果てにある殺人の舞台に選びたくなる、詩情をかきたててくれる街なのだ。
金沢で、前任大学の卒業式に行った。二年前、オーケストラピットで私の指揮を食い入るように見つめた部員たちが卒業する。彼ら、彼女らの演奏を、初めて客席から聴いた。一つの曲に賭ける熱誠のようなものは、おそらく二年前の方があっただろう。だが技術面では長足の進歩が見られた。遙々出向いた甲斐があった。彼ら彼女らの前途洋々たらんことを。
丸二日半、金沢に滞在し、二度の夕食はゼミのOBOG諸君と再会して、楽しい時間となった。奥の束ねT嬢の功績は相変わらず大きい。食べ物が美味いのはうれしいが、集まってくれる面々と、約一年ぶりという時間を感じさせない和やかな会話が、またうれしい。二日目には、M(夫人)が、昨年生まれた長男を連れてきた。何人目かの「内孫」(「ゼミ生の子供」の意)だ。お約束で抱いてみるが、猫と違ってどう抱いて良いやらわからず、すぐに母親に戻す。ゆっくりと進む会食の間、一度も泣くこともなく(外面が良い)、でもちょっと油断するとテーブルに手をかけ、器をひっくり返して母親をパニックに陥れる(実は意地悪)など、母親であるMに似ているらしい(笑)。
二度の昼食は、「うどんこ」で存分に楽しんだ。温冷それぞれのうどんの風味と、絶妙な出汁は、他の追随を許さぬ絶品といえる。今春、ご主人と女将さんの長女が国立大に合格するという慶事も重なり、会話もまた弾む。姉さん(女将さんのこと)は直前に電話で私の予定を確認し、私の好物だったゴボウの天ぷらを作って待っていてくれた。
笹掻きゴボウのかき揚げ。かけうどんの出汁を吸うと得も言われぬ美味さで、私が金沢に住んでいた頃は、冬期間限定ではあるが通常メニューだった。だがこの天ぷらは、下ごしらえに手間がかかりすぎる。限られた人手では対応しきれなかったのか、この冬、ゴボウのかき揚げは店頭に並ばなかった。私と同様にこの天ぷらが好きな吹奏楽部員が頼み込んでも、駄目だったという。ところが二日間だけ、この天ぷらが店に並んだ。事情を知るバイト学生は「奇跡の二日間」と呼んだ。
二年の歳月で、街はずいぶん、その姿を変えた。だが、大好きな人々の温かさと、暮らしにくくて仕方ないメチャクチャな天気は、少しも変わらず、手厚く、手荒く歓迎してくれた。次はいつ、遊びに行こうか。