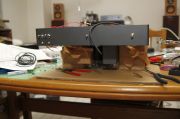2008.06.14 土曜日 22:28
秋葉へ
週末だからといって、余裕をぶっこいていられるはずはないのだが、このところ短時間で決着を着ける(いや、本当は計画的に時間をかければいいのだけれど)作業が多く、健康の問題とあいまっていささかストレスが嵩んだ。疲れているのに眠りが浅く、早朝に目覚めると二度寝が出来ず悶々と・・・。
そこで来週頭に仕上げる予定の用事を総て金曜までにやっつけ、楽しみにしていた「キット屋」さんの東京試聴会にでかけた。過日、刈谷の本社ショールームで視聴させていただき、こちらのキットに一層惚れ込んだのだが、その折に聴くことができなかったアンプ、SPなども登場するということで、勇んで先着順の申し込みを送った。
午前中9時台の特急で東京に出て、ちょっと街を流してから会場に行く予定で動きだした。ところが道中でメールがあり、東北地方の地震を知った。携帯では十分な情報が入らず、新宿のホームで会津に電話する。着信規制もなく通話でき、母の無事を確認。発災と同時に猫たちが飛び出して戻らないとのことで、やはり耐震補強が必要かと、またしても暗澹たる気分。つい先日、屋外の散水、除雪用の井戸を掘り直した(=費用を負担した)ばかりなのに(ToT)。
試聴会の会場は言うまでもなく秋葉。電気街からちょっとだけ神田方向の貸しホールだが、街の雰囲気が微妙にぎこちない。人ごみの向うに献花台のテントが見える。メイド服のお嬢ちゃんが、大声でAED設置のための募金を呼び掛けている。時間まで、街の変貌とはあまり関係ない駅前の小店を覗くと、闇市を思わせる狭い通路の両側に並んだ店先には1コ数十円のパーツ類が整然と並び、むしろ落ち着きすら感じられるから不思議だ。ただ、トランス専門店のおじさんが、値上げが目前に迫っていること、材料高騰で商品の入荷が遅れに遅れていることなど、通り過ぎるだけでは分からない実情を話してくれる。
視聴会場に向かうと、犯行現場が遠望される。重力場が乱れたように(って経験はないけど)重苦しさが波紋になって広がっている。昌平橋を渡ってすぐに会場が見え、汗をかくまでもなく冷房の効いた室内へ。丁度、私が申し込んだ午後の一回目の受付が始まったようだが、会場には既に熱心なファンが大勢いて、思い思いに機器類を眺めている。店主の大橋氏に挨拶し、前の方に座を占めて、開始を待つ。
試聴会は、キット屋さんの代表的パワーアンプを2群に分け、間にスピーカークラフトのウィンズさんのデモを挟む三部構成。私の大好きな送信管中心に多極管とOTLで構成されたB群と、(恐らく)世界一人気の高い真空管300Bを使ったキット屋さんの代表的アンプ群、プラスソ連の6C33というA群。個人的にはB群が面白いが、A群の魅力も捨てがたい。ウィンズさんは必然的にSP主体になるが、私も使っているWE標準箱の本来のサイズ(8インチ用。私のは4インチ用)の鳴りっぷりに感激し、更に小さな箱を鳴らす技術の高さと、低音を補強する小さなトーンコントロールプリの性能に脱帽。ただ、次にキット屋さんで購入するアンプキットは、今回は登場せず、年内に生産中止が決まっている送信管プッシュプルモノラルアンプのペア。この線だだけは動かせない。
各アンプ、SPとソースの組み合わせはそれこそ無数にあり、自分の耳の心地よい組み合わせもあれば、多少疑問の残るセットもあった。だが、何かが悪いというのではなく、飽くまで好みの問題。もっとも極端な場合、真空管という増幅素子を交換するだけで、音は全く別物になる。ハイテク技術の粋を集め、クリーンルームで全自動で作られるLSIとは違った動作になるのも当然だろう。
楽しい90分はあっという間で、改めて電気街のパーツショップや真空管専門店で、現在製作、設計、企画、妄想中などのアンプに使うパーツ類を揃える。有名な専門店で買った良質なパーツが、後で寄った小店で6掛けで売られていてショック。もっとも今回は、高額でも5,000円を越えないトランスと、それこれ数十円の抵抗類が主眼だから、かさばってもあまり懐には響かない。
が、小店から路地に出ると、険悪な空気が。十数人の警官が青年一人を取り囲み、当該青年が甲高い声で悪態をついている。買い物をしたばかりの店の店員氏によると、ドライバーを持って歩いているところを咎められたとか。ここは秋葉だから、奇抜さだけの気味の悪い格好より、工具を持って歩く方がよほど自然だと思うのだが。もちろん、ドライバも振り回したら兇器になる。時節を考え、剥き身で持ち歩くのは止めたまえ。
たんとパーツを買ったから、これから校務がひとつ片付くたびに、一工程か二工程くらい、空いた時間の応じて製作を進めよう。
そこで来週頭に仕上げる予定の用事を総て金曜までにやっつけ、楽しみにしていた「キット屋」さんの東京試聴会にでかけた。過日、刈谷の本社ショールームで視聴させていただき、こちらのキットに一層惚れ込んだのだが、その折に聴くことができなかったアンプ、SPなども登場するということで、勇んで先着順の申し込みを送った。
午前中9時台の特急で東京に出て、ちょっと街を流してから会場に行く予定で動きだした。ところが道中でメールがあり、東北地方の地震を知った。携帯では十分な情報が入らず、新宿のホームで会津に電話する。着信規制もなく通話でき、母の無事を確認。発災と同時に猫たちが飛び出して戻らないとのことで、やはり耐震補強が必要かと、またしても暗澹たる気分。つい先日、屋外の散水、除雪用の井戸を掘り直した(=費用を負担した)ばかりなのに(ToT)。
試聴会の会場は言うまでもなく秋葉。電気街からちょっとだけ神田方向の貸しホールだが、街の雰囲気が微妙にぎこちない。人ごみの向うに献花台のテントが見える。メイド服のお嬢ちゃんが、大声でAED設置のための募金を呼び掛けている。時間まで、街の変貌とはあまり関係ない駅前の小店を覗くと、闇市を思わせる狭い通路の両側に並んだ店先には1コ数十円のパーツ類が整然と並び、むしろ落ち着きすら感じられるから不思議だ。ただ、トランス専門店のおじさんが、値上げが目前に迫っていること、材料高騰で商品の入荷が遅れに遅れていることなど、通り過ぎるだけでは分からない実情を話してくれる。
視聴会場に向かうと、犯行現場が遠望される。重力場が乱れたように(って経験はないけど)重苦しさが波紋になって広がっている。昌平橋を渡ってすぐに会場が見え、汗をかくまでもなく冷房の効いた室内へ。丁度、私が申し込んだ午後の一回目の受付が始まったようだが、会場には既に熱心なファンが大勢いて、思い思いに機器類を眺めている。店主の大橋氏に挨拶し、前の方に座を占めて、開始を待つ。
試聴会は、キット屋さんの代表的パワーアンプを2群に分け、間にスピーカークラフトのウィンズさんのデモを挟む三部構成。私の大好きな送信管中心に多極管とOTLで構成されたB群と、(恐らく)世界一人気の高い真空管300Bを使ったキット屋さんの代表的アンプ群、プラスソ連の6C33というA群。個人的にはB群が面白いが、A群の魅力も捨てがたい。ウィンズさんは必然的にSP主体になるが、私も使っているWE標準箱の本来のサイズ(8インチ用。私のは4インチ用)の鳴りっぷりに感激し、更に小さな箱を鳴らす技術の高さと、低音を補強する小さなトーンコントロールプリの性能に脱帽。ただ、次にキット屋さんで購入するアンプキットは、今回は登場せず、年内に生産中止が決まっている送信管プッシュプルモノラルアンプのペア。この線だだけは動かせない。
各アンプ、SPとソースの組み合わせはそれこそ無数にあり、自分の耳の心地よい組み合わせもあれば、多少疑問の残るセットもあった。だが、何かが悪いというのではなく、飽くまで好みの問題。もっとも極端な場合、真空管という増幅素子を交換するだけで、音は全く別物になる。ハイテク技術の粋を集め、クリーンルームで全自動で作られるLSIとは違った動作になるのも当然だろう。
楽しい90分はあっという間で、改めて電気街のパーツショップや真空管専門店で、現在製作、設計、企画、妄想中などのアンプに使うパーツ類を揃える。有名な専門店で買った良質なパーツが、後で寄った小店で6掛けで売られていてショック。もっとも今回は、高額でも5,000円を越えないトランスと、それこれ数十円の抵抗類が主眼だから、かさばってもあまり懐には響かない。
が、小店から路地に出ると、険悪な空気が。十数人の警官が青年一人を取り囲み、当該青年が甲高い声で悪態をついている。買い物をしたばかりの店の店員氏によると、ドライバーを持って歩いているところを咎められたとか。ここは秋葉だから、奇抜さだけの気味の悪い格好より、工具を持って歩く方がよほど自然だと思うのだが。もちろん、ドライバも振り回したら兇器になる。時節を考え、剥き身で持ち歩くのは止めたまえ。
たんとパーツを買ったから、これから校務がひとつ片付くたびに、一工程か二工程くらい、空いた時間の応じて製作を進めよう。