2008.02.18 月曜日 20:39
重ね重ねオーディオ機器を作る
・『無辜の不処罰』は近代刑事訴訟の鉄則。時に下っ端がこれを忘れて大問題を起こすが、法相が「知ってんの?」と思われるようでは問題外。
・可処分所得が増えず、税は上がり、燃料も小麦も暴騰するとなると、今年は春が来るのか本気で不安になる。このご時勢でも「景気は拡大し続けている」などと空念仏を唱えるだけなら、上から見ると『円』に見えるという皮肉な建物の主なんか、国会の同意人事にしなくてもいい。
・臨時の帰省も早や10日。二月にこんなに長く会津にいるのは、おそらく修士2年のころ、当時の猫が重い病気になり看病に呼び戻されて以来。数日前までは多分雪だった、軒下に積もる氷の塊を掻き出すのに、つるはしを振るう。箸と六法より重いものは持たない主義なのに・・・。
憧れの送信管アンプ(その5)
憧れのアンプに取り組み、興奮で眠れないかと思ったが、疲れのほうが予想以上で、翌日はゆっくりと起床。今回の作業場に設定したリビングに移動すると、テーブルの上はもちろん、カーペットの上もいろいろなものが飛び散り、文字通りの惨状を呈している。BGMを流し、コーヒーを淹れ、新聞を開いて見出しを追うがほとんど頭に入らない。目の前には、作りかけの大型アンプが仰向けに置かれているのだから、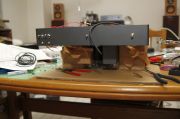 このアンプ以外のことを考えろというほうが無理。マニュアルを開き今日の作業の手順を確認する。
このアンプ以外のことを考えろというほうが無理。マニュアルを開き今日の作業の手順を確認する。
脳みそと筋肉が動き出すのを待ちきれず、はんだごてに火を入れ、楽しさと不安とを半々に抱えながら、最初の手順にかかる。天板を下にして組み込んでいくわけで、アース、ヒーター、整流回路からB電源、信号系と、組み付けた大型部品の端子、ラグをワイヤーでつないでいく。イメージとしては、基盤のパターンをワイヤーで作っていく感じ。だが、ひとつのラグの穴にいくつも部品やワイヤーが入る箇所もあり、後に来るパーツを考えながら、場合によっては爪楊枝で穴を確保しながら半田を盛っていく。面倒な作業が続くが、実に楽しい。
ワイヤーによる配線が終わった時点で、いったん作業を止めて間違い探し。すべての配線を回路図と実体図と照合する。ミスは見つからず、CR類のはんだ付けに進む。手順では電源系から組んでいく。倍電圧整流のためのダイオードは、内蔵するブロックコンデンサの端子とラグで取り付ける。かなりの電流が流れ発熱が予想される大型のホーロー抵抗をつなぎ、チョークコイルとコンデンサ、ブリーダ抵抗などをはんだ付けしていく 。1000Vを安定して供給する電源部は大き目の部品が多く、必然的に高密度実装となる。技術も経験もない身には大変に難しい。レイアウト上は電源部に近いシャーシ奥に、4本のセメント抵抗を付ける。出力管の845、または211のバイアスを決める重要な抵抗だが、これも非常に熱を出す。また、二種類の真空管を挿し換える時には、ここの抵抗をスイッチで切り替えてバイアスを変える。
。1000Vを安定して供給する電源部は大き目の部品が多く、必然的に高密度実装となる。技術も経験もない身には大変に難しい。レイアウト上は電源部に近いシャーシ奥に、4本のセメント抵抗を付ける。出力管の845、または211のバイアスを決める重要な抵抗だが、これも非常に熱を出す。また、二種類の真空管を挿し換える時には、ここの抵抗をスイッチで切り替えてバイアスを変える。
・可処分所得が増えず、税は上がり、燃料も小麦も暴騰するとなると、今年は春が来るのか本気で不安になる。このご時勢でも「景気は拡大し続けている」などと空念仏を唱えるだけなら、上から見ると『円』に見えるという皮肉な建物の主なんか、国会の同意人事にしなくてもいい。
・臨時の帰省も早や10日。二月にこんなに長く会津にいるのは、おそらく修士2年のころ、当時の猫が重い病気になり看病に呼び戻されて以来。数日前までは多分雪だった、軒下に積もる氷の塊を掻き出すのに、つるはしを振るう。箸と六法より重いものは持たない主義なのに・・・。
憧れの送信管アンプ(その5)
憧れのアンプに取り組み、興奮で眠れないかと思ったが、疲れのほうが予想以上で、翌日はゆっくりと起床。今回の作業場に設定したリビングに移動すると、テーブルの上はもちろん、カーペットの上もいろいろなものが飛び散り、文字通りの惨状を呈している。BGMを流し、コーヒーを淹れ、新聞を開いて見出しを追うがほとんど頭に入らない。目の前には、作りかけの大型アンプが仰向けに置かれているのだから、
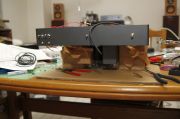 このアンプ以外のことを考えろというほうが無理。マニュアルを開き今日の作業の手順を確認する。
このアンプ以外のことを考えろというほうが無理。マニュアルを開き今日の作業の手順を確認する。脳みそと筋肉が動き出すのを待ちきれず、はんだごてに火を入れ、楽しさと不安とを半々に抱えながら、最初の手順にかかる。天板を下にして組み込んでいくわけで、アース、ヒーター、整流回路からB電源、信号系と、組み付けた大型部品の端子、ラグをワイヤーでつないでいく。イメージとしては、基盤のパターンをワイヤーで作っていく感じ。だが、ひとつのラグの穴にいくつも部品やワイヤーが入る箇所もあり、後に来るパーツを考えながら、場合によっては爪楊枝で穴を確保しながら半田を盛っていく。面倒な作業が続くが、実に楽しい。
ワイヤーによる配線が終わった時点で、いったん作業を止めて間違い探し。すべての配線を回路図と実体図と照合する。ミスは見つからず、CR類のはんだ付けに進む。手順では電源系から組んでいく。倍電圧整流のためのダイオードは、内蔵するブロックコンデンサの端子とラグで取り付ける。かなりの電流が流れ発熱が予想される大型のホーロー抵抗をつなぎ、チョークコイルとコンデンサ、ブリーダ抵抗などをはんだ付けしていく
 。1000Vを安定して供給する電源部は大き目の部品が多く、必然的に高密度実装となる。技術も経験もない身には大変に難しい。レイアウト上は電源部に近いシャーシ奥に、4本のセメント抵抗を付ける。出力管の845、または211のバイアスを決める重要な抵抗だが、これも非常に熱を出す。また、二種類の真空管を挿し換える時には、ここの抵抗をスイッチで切り替えてバイアスを変える。
。1000Vを安定して供給する電源部は大き目の部品が多く、必然的に高密度実装となる。技術も経験もない身には大変に難しい。レイアウト上は電源部に近いシャーシ奥に、4本のセメント抵抗を付ける。出力管の845、または211のバイアスを決める重要な抵抗だが、これも非常に熱を出す。また、二種類の真空管を挿し換える時には、ここの抵抗をスイッチで切り替えてバイアスを変える。
奥側の電源部、中ほどにバヨネット式ソケット、シャーシ手前には初段とドライブ段の真空管4本のためのソケットが付く。電源の更に奥、背面に付けたRCAプラグから入った信号をシールド線で入力VRに導き、そこから初段管(双三極管12AX7をパラレルで)のグリッドに入る。太いシールド線を小さなMT9Pソケットに付けるのは、慣れた人でも難しいだろう。パラレル接続のため、3本のメッキ線にガラスチューブをかけて取り付けてあるから、端子の穴は非常に狭くなっている。その上、バイアス抵抗と並列するコンデンサ、グリッド抵抗、カップリングコンデンサ、B電圧減衰用の抵抗など、取り付ける部品は多い。
ドライブ段には、夕べ、大いに焦りながらも冷静を装い(?)、助手に手伝ってもらって用意した2kΩの抵抗
 をはじめ、初段と同様に多くの部品を取り付ける。一回り大きな容量が指定されたカップリングコンデンサを二つのソケットの間にはんだ付けするが、どうも格好が悪い。きれいな直角が出ていないのが原因だが、立体的な配置で直角を保つのは、ビギナーには至難の業。
をはじめ、初段と同様に多くの部品を取り付ける。一回り大きな容量が指定されたカップリングコンデンサを二つのソケットの間にはんだ付けするが、どうも格好が悪い。きれいな直角が出ていないのが原因だが、立体的な配置で直角を保つのは、ビギナーには至難の業。そしてここで、愛用のはんだが足りなくなってきた。秋葉でまとめ買いした銀入りはんだを使っているが、いくつも連続してキットを作るのだから、なくなるのも当然。またまた、はやる気持ちを抑え、いったん休憩して近所のホームセンターに。同じメーカーの銀入りはんだを買い、ついでに食料も少々調達して帰宅する。
帰宅後はすぐに作業を再開。だが、買ってきたはんだは、もとのものと組成が違っていた。ために前に付けた予備はんだと新しいはんだが馴染み難い。パーツへのダメージを考えると短時間にはんだごてを離したいが、はんだが馴染んでくれないと接触不良は必死。部分的に前のはんだを吸い取ったり、余計な作業が増え、だんだんとはんだ付け箇所と周辺部品が汚くなってくる。
苦心惨憺の末、すべての部品を付け終わると、もう夕食時を過ぎている。
 だが、食事のために次の大切なステップを先延ばしにはできない。緊張で心拍数が上がっているが、再度間違いがないか最初からチェックを行い、ノーミスであることを確認して、火入れ式に進む。
だが、食事のために次の大切なステップを先延ばしにはできない。緊張で心拍数が上がっているが、再度間違いがないか最初からチェックを行い、ノーミスであることを確認して、火入れ式に進む。式といっても、祝詞をあげるわけではなく、もしかしたら高圧を受けた部品が爆発するかも、という危険を冒して、でも十分に避けられる用意をしてから、初めて通電すること。真空管を挿さずにスタンバイスイッチを入れ、ヒューズが切れないか、煙は出ないか、異臭はしないか、緊張の数秒間の後、テスターでフィラメント、ヒーターの電圧を測る。まだ1000Vは来ていないが、ヒーター回路には高い電流が流れているから、下手なことをすると感電する。負荷がないからやや高めに電圧が出るが、これは正常。スイッチを切り、3種6本の真空管を取り付けて改めてスタンバイスイッチを入れて同じように電圧を測る。すでにトリタンフィラメントは眩しいほど輝いている。電圧は正常。
再度電源を切り、スピーカの代わりにダミー抵抗を付け、スタンバイスイッチを入れる。ヒーターが温まるのを見計らって、パワースイッチを入れる。このスイッチで最高約1000VのB電源が動き出し、真空管は動作を開始する。パーツの爆発も、発煙もない。先端1mmだけ残してテープで絶縁したテスター棒を、恐る恐る所定の端子に当てて各部の電圧を測る。若干のずれはあるが、問題はない。
ついに、スピーカをつなぐ段階にきた。アルテックの404-8Aを両チャネルにつなぎ、CDの信号を入れ、ボリュームを上げる。が、音が出ない。一気に血圧が上がり、汗が噴き出す。パワースイッチを切ってスピーカをはずし、電圧を測るが異常はない。再度スピーカをつなぎ、ゆっくりとボリュームを上げていくと、ブーンというハムノイズと一緒に音楽が聞こえてきた。結局、最初に音が出なかったのは、スピーカ側の結線が間違っていたのだが、一瞬頭の中が真っ白になった。音楽を止め、片チャンネルずつスピーカをつなぎ、ハムバランサを調整すると、あっさりとハムが消える。両チャンネルともハムを消し、とりあえず、丸二日に及ぶ組立作業は終了した。作業に間違いがないことをもう一度確かめ、シャーシの中を縦横に走っているワイヤーを、可能な限り丁寧に結束する。
 初めての「大物」で、ワイヤーの長さをあわせる余裕がなく、結果、結束しても見苦しい。次回は是非、きれいな結線を心がけよう。
初めての「大物」で、ワイヤーの長さをあわせる余裕がなく、結果、結束しても見苦しい。次回は是非、きれいな結線を心がけよう。
底板を付け、ラックの最上段に乗せると、その威容が引き立つ。これから100時間程度は、本格的な音出しはできず、真空管のエージングになる。今夜はスタンバイスイッチを入れたまま、明日朝の音を楽しみに休むことにしよう。
散らかりまくったリビングをざっと片付け、軽く食事をすると、一気に疲れが噴出してくる。本当はまだまともな音は出ないのだが、ちょっとだけ音を聞いてみると、非常に透明度の高い高音が。これが送信管アンプの音か。これまでのビーム管とはまったく違う種類の音がする。
奥が深いというよりも、これは底なし沼だと気づいたが、もう遅かった。
comments