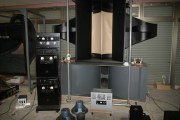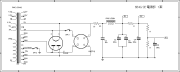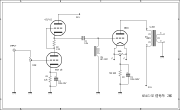2010.05.08 土曜日 22:12
しっとりオーディオ機器を作る
嘘。今回は作ってない。
ということで
番外編 TL51X を買った
愛用のCDプレーヤー"SANSUI CD-α717DR"を買ったのは、まだバブルの余韻が残る頃。大学院生ながらバブリーなお仕事で纏まったお宝を頂戴し、現在でも私のリファレンス機であるアンプ、スピーカと一緒に購入した。このプレーヤー、最先端の1bitDACを搭載し、高い剛性のシャーシと相まって、鮮やかな色彩感と光沢を放ちながらも決してギラつかない音を聴かせてくれた。その後、湿気との長い戦いを生き抜き、トレイに動力を伝えるベルトは何度交換したか知れない。最近では、バンコードという特殊ゴムを買ってきて、「専用輪ゴム」まで自作していた。
だが本来、回る物の耐用年数は決して長くない。20年に垂んとする長い時を経て、このプレーヤーも本来の性能を発揮することができなくなってきた。手(ピックアップを制御するモーター類)が震え、目(光学ピックアップ)がかすみ、正しくデータを読み取れない場面が、目に見えて増えたのだ。サブのプレーヤー1台、DVDなどマルチディスクプレーヤー3台、パソコン用のドライブに至っては無数に転がっているこの部屋だが、このリファレンス機に匹敵する音を出す機械は持っていない。いよいよ新しい機械を買うしかなさそうだ。
そうは思っても、忙しさにかまけ、かつ完成品を買う事への微妙な感情もあって一日延ばしにしていたのだが、数日前のこと、刈谷のキット屋さんのHPで、あるプレーヤーが製造中止になるというニュースに接した。漠然と「買うならこれ」と決めていた"CEC TL51X"だ。
DACはキット屋さんから購入し組み立てた "Model2" を愛用しているが、このDACとの相性が良いと評判であり、刈谷の試聴室でも、東京の試聴会でも何度となく聴いた「あの音」なら、新たな常用プレーヤーとして必要十分だ。SACDも普及は見込めそうもないし、ここで単体のトランスポート(DACを持たず、ディスクからデジタル信号を取り出す)を買うのもエレクトロニクスおやじらしくていい。そのトランスポートがキット屋さんに10台程度、メーカー在庫も同数くらいで、既に製造を中止したらしい。怒る元気も失せる。
キット屋さんでは受注を止め、日時を決めて一斉に注文を受けるという。キット屋さんのこの方法でまともに買えたことはない。何故か販売開始の時刻、用事があってパソコンに向かえないのだ。では、どこか在庫を持っているところはないだろうか、と、とりあえずググってみたところ、アマゾン経由で地方のショップが「在庫あり」の表示を出している。アマゾンなら支払いも簡単だし、割引率はキット屋さんと同じ。送料無料ならいうことない。瞬間に購入を決意し、幾つかのボタンを押して注文を確定させた。これが、4月23日金曜日午前8時のこと。恐らく注文が駆け巡っているだろうから、果たして買えるかどうか。
アマゾンのオートコンファメーションはすぐに届いたが、販売するショップから連絡が来たのはその日の午後6時半。メールに曰く
週が明け、26日月曜日の午前中、件のショップから
その後も若干気を揉んだが、今朝、無事にブツが届いた。アマゾンに注文し、地方のショップが受注、メーカーに直送を手配した。メーカーは他県の物流センターから送り出し、指定日まで一晩、甲府のクロネコで留め置かれて届けられたのは、この機体。
 本体の上にある黒い物体は、CDの上に載せるスタビライザ。ボタンを押すとトレイが出てきたりディスクを吐き出したりするのではなく、手で上部のフタを押して開ける。
本体の上にある黒い物体は、CDの上に載せるスタビライザ。ボタンを押すとトレイが出てきたりディスクを吐き出したりするのではなく、手で上部のフタを押して開ける。

非常に"アナログ"な作りだ。だが、トップローディングということは、筐体の上方に十分な空間がないとディスクの出し入れに困る。だが私が使う(作る)真空管アンプは、基本的に上部に真空管を露出させる(変な趣味じゃなくって放熱のためだからねっ!)から、最上部に51Xを置くことができない。困った挙げ句に辿り着いたのは、元のプレーヤーと入れ替え、棚板を若干上げて手が入るようにするという、あまり美的ではない解決策。

TL51Xは世界的にも珍しいベルトドライブ方式を採用している。ダイレクトドライブでは避けることのできない駆動による振動をキャンセルし、外周と内周で異なる回転数を正確に、シームレスに変化させる。低トルクモーターと、300gのスタビライザによる慣性モーメントを利用しているとあるが、力学は今ひとつ理解しにくいな(^^ゞ
午前中に届き、すぐにラックまわりの掃除と配線し直し、同時に現在のメインアンプ(ブログ未搭載)の電源スイッチ調整を済ませ、急いで音を出したわけだが、鮮明な音、奥だけでなく手前、リスナーに向かって音像が広がるような感覚。リジットな駆動部分のおかげでエラーのないデータ読み取りが行われ、真空管バッファ付きDAコンバータの威力が遺憾なく発揮されている。鮮度の高い音、とでも表現しておこうか。これまでも十分に満足できる音だったが、更に一皮むけた、一ランク上の生き生きした音場が出現した。ここの楽器がくっきり聞こえるだけでなく、オケの、アンサンブルの広さ、奥行きまでよりはっきりと見えるようになった。
このトランスポートなら、DACを換えることで更に変化を楽しめるだろう。デジタル臭さはそもそもないが、最近気に入っているトランスを使っても間違いなく楽しめる。バラック組みで止まっているトランス出力プリアンプ、送信管アンプ、真空管バッファ付きチューナーと並行してDAC第三号を検討するかな…
バキッ!!☆/(x_x)
ということで
番外編 TL51X を買った
愛用のCDプレーヤー"SANSUI CD-α717DR"を買ったのは、まだバブルの余韻が残る頃。大学院生ながらバブリーなお仕事で纏まったお宝を頂戴し、現在でも私のリファレンス機であるアンプ、スピーカと一緒に購入した。このプレーヤー、最先端の1bitDACを搭載し、高い剛性のシャーシと相まって、鮮やかな色彩感と光沢を放ちながらも決してギラつかない音を聴かせてくれた。その後、湿気との長い戦いを生き抜き、トレイに動力を伝えるベルトは何度交換したか知れない。最近では、バンコードという特殊ゴムを買ってきて、「専用輪ゴム」まで自作していた。
だが本来、回る物の耐用年数は決して長くない。20年に垂んとする長い時を経て、このプレーヤーも本来の性能を発揮することができなくなってきた。手(ピックアップを制御するモーター類)が震え、目(光学ピックアップ)がかすみ、正しくデータを読み取れない場面が、目に見えて増えたのだ。サブのプレーヤー1台、DVDなどマルチディスクプレーヤー3台、パソコン用のドライブに至っては無数に転がっているこの部屋だが、このリファレンス機に匹敵する音を出す機械は持っていない。いよいよ新しい機械を買うしかなさそうだ。
そうは思っても、忙しさにかまけ、かつ完成品を買う事への微妙な感情もあって一日延ばしにしていたのだが、数日前のこと、刈谷のキット屋さんのHPで、あるプレーヤーが製造中止になるというニュースに接した。漠然と「買うならこれ」と決めていた"CEC TL51X"だ。
DACはキット屋さんから購入し組み立てた "Model2" を愛用しているが、このDACとの相性が良いと評判であり、刈谷の試聴室でも、東京の試聴会でも何度となく聴いた「あの音」なら、新たな常用プレーヤーとして必要十分だ。SACDも普及は見込めそうもないし、ここで単体のトランスポート(DACを持たず、ディスクからデジタル信号を取り出す)を買うのもエレクトロニクスおやじらしくていい。そのトランスポートがキット屋さんに10台程度、メーカー在庫も同数くらいで、既に製造を中止したらしい。怒る元気も失せる。
キット屋さんでは受注を止め、日時を決めて一斉に注文を受けるという。キット屋さんのこの方法でまともに買えたことはない。何故か販売開始の時刻、用事があってパソコンに向かえないのだ。では、どこか在庫を持っているところはないだろうか、と、とりあえずググってみたところ、アマゾン経由で地方のショップが「在庫あり」の表示を出している。アマゾンなら支払いも簡単だし、割引率はキット屋さんと同じ。送料無料ならいうことない。瞬間に購入を決意し、幾つかのボタンを押して注文を確定させた。これが、4月23日金曜日午前8時のこと。恐らく注文が駆け巡っているだろうから、果たして買えるかどうか。
アマゾンのオートコンファメーションはすぐに届いたが、販売するショップから連絡が来たのはその日の午後6時半。メールに曰く
当店のシステムの都合により、午前9時以降のご注文につきましてはキレそうになった。国内で1時間も時差があるって、どこだ、一体!
翌営業日のご注文確認後のご案内となります。
週が明け、26日月曜日の午前中、件のショップから
ご注文頂きました商品ですが、ご注文が殺到しており当店在庫切れとなってしまいました。誠に申し訳御座いません。と行って寄越した。買えなかったら、このメーカーの他機種(価格は三割り増しくらい(;_:))にするか…。ところが5時間後、受注確認のメールが入った。といっても発送に関する記述が曖昧で、確実に購入できるのかどうか判然としない。そこで、配送を連休明けにして欲しい旨、メールを送ってみた。すると翌日、着日指定で手配したとの返信が届いた。どうやら頑張ってメーカーと交渉してくれたようだ。ちなみにキット屋さんでは瞬時に売り切れたらしい。
現在、商品確保の為メーカーと交渉中で御座います。
その後も若干気を揉んだが、今朝、無事にブツが届いた。アマゾンに注文し、地方のショップが受注、メーカーに直送を手配した。メーカーは他県の物流センターから送り出し、指定日まで一晩、甲府のクロネコで留め置かれて届けられたのは、この機体。
 本体の上にある黒い物体は、CDの上に載せるスタビライザ。ボタンを押すとトレイが出てきたりディスクを吐き出したりするのではなく、手で上部のフタを押して開ける。
本体の上にある黒い物体は、CDの上に載せるスタビライザ。ボタンを押すとトレイが出てきたりディスクを吐き出したりするのではなく、手で上部のフタを押して開ける。
非常に"アナログ"な作りだ。だが、トップローディングということは、筐体の上方に十分な空間がないとディスクの出し入れに困る。だが私が使う(作る)真空管アンプは、基本的に上部に真空管を露出させる(変な趣味じゃなくって放熱のためだからねっ!)から、最上部に51Xを置くことができない。困った挙げ句に辿り着いたのは、元のプレーヤーと入れ替え、棚板を若干上げて手が入るようにするという、あまり美的ではない解決策。

TL51Xは世界的にも珍しいベルトドライブ方式を採用している。ダイレクトドライブでは避けることのできない駆動による振動をキャンセルし、外周と内周で異なる回転数を正確に、シームレスに変化させる。低トルクモーターと、300gのスタビライザによる慣性モーメントを利用しているとあるが、力学は今ひとつ理解しにくいな(^^ゞ
午前中に届き、すぐにラックまわりの掃除と配線し直し、同時に現在のメインアンプ(ブログ未搭載)の電源スイッチ調整を済ませ、急いで音を出したわけだが、鮮明な音、奥だけでなく手前、リスナーに向かって音像が広がるような感覚。リジットな駆動部分のおかげでエラーのないデータ読み取りが行われ、真空管バッファ付きDAコンバータの威力が遺憾なく発揮されている。鮮度の高い音、とでも表現しておこうか。これまでも十分に満足できる音だったが、更に一皮むけた、一ランク上の生き生きした音場が出現した。ここの楽器がくっきり聞こえるだけでなく、オケの、アンサンブルの広さ、奥行きまでよりはっきりと見えるようになった。
このトランスポートなら、DACを換えることで更に変化を楽しめるだろう。デジタル臭さはそもそもないが、最近気に入っているトランスを使っても間違いなく楽しめる。バラック組みで止まっているトランス出力プリアンプ、送信管アンプ、真空管バッファ付きチューナーと並行してDAC第三号を検討するかな…
バキッ!!☆/(x_x)