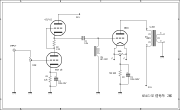2008.10.09 木曜日 20:54
牛乳よ、お前もか?
バナナが好きだというと、よく馬鹿にされた。珍しくもなく、極端に糖度が高いわけでもなく、至って安価な果物で、あえて「好きだ」というほどのものではない、と、見られているのだろう。だが、手っ取り早い炭水化物摂取法として知られ、歴史上の知識として、病気にならなければ食べられない貴重品だった過去もある。
ところが全国的なブームのせいで、ここ甲府でも「品切れ」「品薄」が続いている。型がよく、味も濃厚な「高級品」には、とんとお目にかかれなくなった。急激な需要に対応しようにも、何分輸入品だから、今日明日に流通量を増やすわけにはいかない。納豆の悲劇も記憶に新しいから、関係者も判断に困るのではないだろうか。
そんな折から、こんなニュースを見た。これはかなりマズい。今年の上半期、バターの品薄を解消するため、メーカーや農協が原乳の増産をもとめようとしても、乳牛の処分を含む減産を実施した後だったので、酪農家を怒らせるだけだったとか。この上「ダイエット」などという甘美な冠が乗ってしまったら、とんでもないことになるかもしれない。朝食にバナナ牛乳を飲むのが流行り、一気に品薄に陥ったらどうしよう。好物の低温殺菌牛乳や、脂肪分の高い加工乳が買えなくなったら非常に寂しい。
ただ、私の体型は、バナナとも牛乳とも無関係だと断言できる。
ところが全国的なブームのせいで、ここ甲府でも「品切れ」「品薄」が続いている。型がよく、味も濃厚な「高級品」には、とんとお目にかかれなくなった。急激な需要に対応しようにも、何分輸入品だから、今日明日に流通量を増やすわけにはいかない。納豆の悲劇も記憶に新しいから、関係者も判断に困るのではないだろうか。
そんな折から、こんなニュースを見た。これはかなりマズい。今年の上半期、バターの品薄を解消するため、メーカーや農協が原乳の増産をもとめようとしても、乳牛の処分を含む減産を実施した後だったので、酪農家を怒らせるだけだったとか。この上「ダイエット」などという甘美な冠が乗ってしまったら、とんでもないことになるかもしれない。朝食にバナナ牛乳を飲むのが流行り、一気に品薄に陥ったらどうしよう。好物の低温殺菌牛乳や、脂肪分の高い加工乳が買えなくなったら非常に寂しい。
ただ、私の体型は、バナナとも牛乳とも無関係だと断言できる。